個人事業主に必要な建設業の届出とは?押さえるべきポイント

この記事の要約
- 建設業の「届出」と「許可」の違いを解説
- 個人事業主に関わる主な届出・登録を紹介
- 届出の手続きと怠った場合の罰則を説明
- 目次
- 建設業における「届出」とは?「許可」「登録」との違いを解説
- 建設業許可(許可)との根本的な違い
- 「届出」と「登録」の違い
- [表で整理] 許可・登録・届出の比較
- 届出や許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
- 個人事業主が確認すべき建設業の主な「届出」と「登録」
- ① 解体工事業登録
- ② 電気工事業の登録・届出
- ③ 浄化槽工事業の登録・届出
- 建設業の届出・登録手続きで押さえるべきポイント
- ポイント①:届出先(提出先)はどこか?
- ポイント②:必要な要件(技術管理者など)
- ポイント③:必要書類と作成の注意点
- ポイント④:届出・登録にかかる費用(手数料)
- ポイント⑤:有効期間と更新の必要性
- 必要な届出を怠った場合の罰則・リスク
- 法律違反による罰則
- 取引上の信用失墜
- 届出で十分?「建設業許可」取得を検討すべきタイミング
- 500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合
- 元請けとして他の下請け業者を使いたい場合
- 公共工事の入札に参加したい場合
- まとめ:個人事業主は「許可」と「届出」の判断が重要
- 建設業の届出に関するよくある質問
建設業における「届出」とは?「許可」「登録」との違いを解説
建設業を営む上で、「許可」「登録」「届出」という似た言葉が出てきます。これらは明確に異なる制度であり、個人事業主として事業を行う上で、どの手続きが必要かを正確に把握することが重要です。特に「建設業許可」が不要な小規模工事であっても、「届出」や「登録」が必須となるケースがあるため注意が必要です。
建設業許可(許可)との根本的な違い
建設業許可(許可)は、一定規模以上(原則として税込500万円以上)の建設工事を請け負うために必要な「参入資格」です。これは建設業法に基づき、一定の経営基盤や技術力があることを証明し、国土交通大臣または都道府県知事から「許可」を得るものです。
対して「届出」は、特定の業務を行う事実を行政機関(都道府県など)に「知らせる」行為です。許可のような厳格な審査や財産的要件は求められないことが多いですが、その業務を行う上での最低限のルール(例:特定の資格者の配置)を守ることを前提としています。許可が「事業を行うための資格」であるのに対し、届出は「特定の業務を行うことの報告」という違いがあります。
「届出」と「登録」の違い
「届出」とよく似た手続きに「登録」があります。これも特定の専門工事(例:解体工事業)を行うために必要な手続きです。
「登録」は、「届出」よりも厳格な側面を持ちます。単に「知らせる」だけでなく、行政機関の「名簿に載せる」イメージです。登録にあたっては、業務を適正に行える技術管理者の配置などが要件とされる場合が多く、「届出」よりも参入要件が厳しい傾向にあります。建設業許可が不要な500万円未満の工事であっても、専門工事の種類によってはこの「登録」が必須となります。
[表で整理] 許可・登録・届出の比較
これら3つの違いを理解するために、目的や要件を比較表にまとめます。
許可・登録・届出の比較表
| 項目 | 建設業許可 | 登録 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一定規模以上の工事の許可 | 特定専門工事の資格 | 業務開始等の報告 |
| 必要なケース | 500万円以上の工事を請け負う場合 | 解体工事業、浄化槽工事業など | 電気工事業(みなし)、特例浄化槽工事業など |
| 要件 | 経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など | 各業法に定める技術管理者など | 各業法に定める要件 |
| 罰則 | 無許可営業は重い(懲役刑など) | 登録・届出違反は過料など | 登録・届出違反は過料など |
届出や許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
個人事業主の多くは、「建設業許可」が不要な範囲で事業を行っています。これは建設業法で定められた「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。この範囲内であれば、元請け・下請けを問わず建設業許可は必要ありません。
ただし、後述するように、軽微な建設工事であっても専門工事の種類によっては「登録」や「届出」が必要になるため、注意が必要です。
- 軽微な建設工事の定義
・ 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事。または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
・ 建築一式工事以外の工事(例:内装工事、塗装工事など):工事1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事。
[出典:[建設業法 第三条 | e-Gov法令検索]]
個人事業主が確認すべき建設業の主な「届出」と「登録」
請負金額が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを行う個人事業主であっても、以下の専門工事を行う場合は、建設業許可とは別に各専門業法に基づく「登録」や「届出」が必要です。自身の業務が該当しないか必ず確認してください。
① 解体工事業登録
500万円未満の解体工事(軽微な建設工事)を請け負う場合に必要な手続きです。これは建設業法ではなく、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく「登録」です。
建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得している場合は、この登録は不要ですが、許可を持っていない個人事業主が解体工事を行う場合は必須となります。登録には、一定の基準を満たす技術管理者(実務経験や特定の資格)を選任する必要があります。
[出典:[解体工事業登録について | 国土交通省]]
② 電気工事業の登録・届出
一般用電気工作物(住宅や小規模店舗の屋内配線など)や自家用電気工作物(小規模な工場など)の電気工事を行う場合、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく手続きが必要です。
・ 登録電気工事業者(登録):建設業許可を持っていない事業者が電気工事を行う場合。
・ みなし登録電気工事業者(届出):建設業許可(電気工事業)を持っている事業者が電気工事を行う場合。
個人事業主で建設業許可を持っていない場合は、「登録」が必要となります。この登録にも、第一種・第二種電気工事士の免状を持つか、一定の実務経験を持つ主任電気工事士を配置する必要があります。
[出典:[電気工事業法(手続) | 経済産業省]]
③ 浄化槽工事業の登録・届出
浄化槽の設置(据付け)や保守点検、清掃を行う場合、「浄化槽法」に基づく手続きが必要です。
・ 浄化槽工事業登録(登録):浄化槽の設置工事を行う場合。
・ 特例浄化槽工事業者届出(届出):建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を持っている事業者が浄化槽工事を行う場合。
個人事業主で関連する建設業許可を持っていない場合は、「登録」が必要です。登録には、浄化槽設備士の資格を持つ者を技術管理者として配置することが求められます。
[出典:[浄化槽工事業の登録制度について | 環境省]]
建設業の届出・登録手続きで押さえるべきポイント
これらの「届出」や「登録」を行う際、共通して押さえておくべき手続き上のポイントを解説します。手続きをスムーズに進めるため、事前に流れを把握しておきましょう。
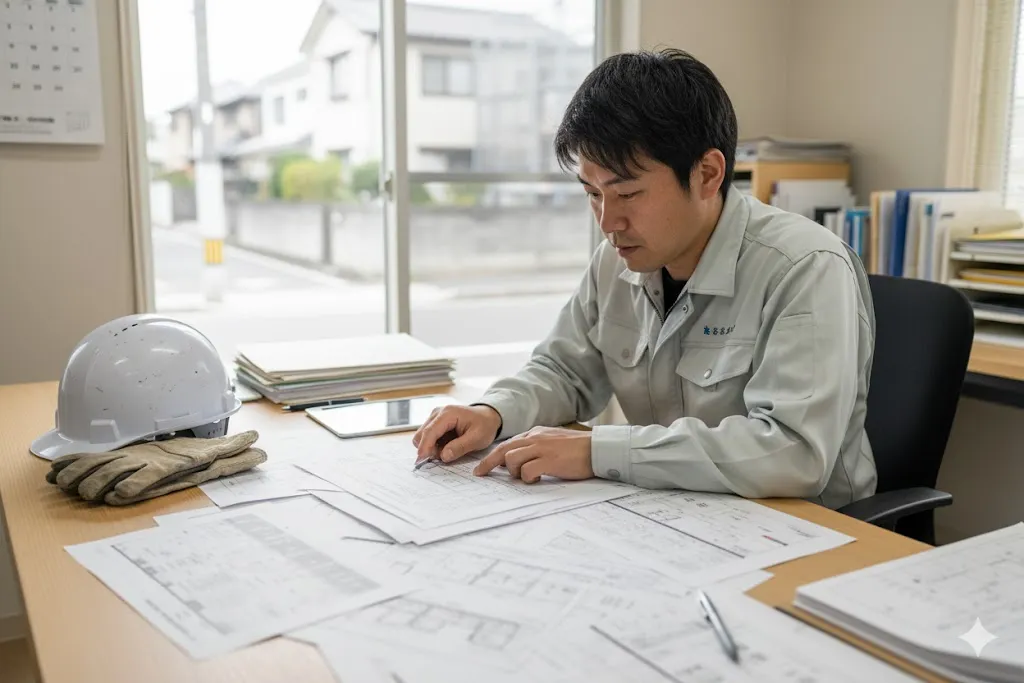
ポイント①:届出先(提出先)はどこか?
手続きの窓口は、行う業務や営業所の所在地によって異なります。
・ 一般的な窓口:営業所の所在地を管轄する都道府県の担当部署(例:土木事務所、各業法の担当課など)が一般的です。
・ 注意点:複数の都道府県で営業を行う場合でも、個人事業主の場合は通常、主たる営業所のある都道府県への届出・登録で問題ないケースが多いですが、詳細は各法律や自治体の規定を確認する必要があります。
ポイント②:必要な要件(技術管理者など)
「届出」や「登録」には、その業務を適正に行うための専門知識や技術を持つ責任者の配置が必須とされます。
・ 技術管理者(例):
・ 解体工事業登録:一定の実務経験者や、土木施工管理技士、建築施工管理技士、解体工事施工技士などの有資格者。
・ 電気工事業登録:第一種または第二種電気工事士(免状取得後3年以上の実務経験が必要な場合あり)。
・ 浄化槽工事業登録:浄化槽設備士。
これらの要件を満たす人材(個人事業主本人または従業員)がいないと、手続き自体ができません。
ポイント③:必要書類と作成の注意点
提出する書類は多岐にわたるため、漏れなく準備する必要があります。
- 一般的な必要書類の例
- 登録申請書または届出書(指定様式)
- 誓約書(法律で定められた欠格要件に該当しないことを誓約する書類)
- 技術管理者の資格を証明する書類(資格者証、免状の写し、実務経験証明書など)
- 技術管理者の常勤性を確認する書類
- 申請者の住民票の写し(個人事業主の場合)
- 営業所が適切であることを示す書類(賃貸借契約書の写しなど)
※これらは一例です。必要な書類は行う業務や自治体によって異なります。必ず事前に管轄窓口のウェブサイトや手引きで確認してください。
ポイント④:届出・登録にかかる費用(手数料)
手続きには法定の手数料や登録免許税がかかる場合があります。
・ 費用(例):数万円程度の登録手数料や登録免許税が必要となることが多いです(例:解体工事業登録は3〜4万円程度が目安)。
・ その他:住民票や登記されていないことの証明書など、添付書類の取得費用も別途必要です。
ポイント⑤:有効期間と更新の必要性
これらの届出・登録の多くは、一度行えば永久に有効というわけではありません。
・ 有効期間:多くの場合、5年間の有効期間が定められています。
・ 更新手続き:有効期間が満了する前に、更新の手続きが必要です。更新を忘れると資格が失効し、そのまま業務を続けると無登録・無届出営業となってしまうため、厳重な管理が求められます。
必要な届出を怠った場合の罰則・リスク
「軽微な工事だから」「500万円未満だから」と軽く考え、必要な届出や登録を怠ると、事業継続に関わる重大なリスクを負うことになります。個人事業主であっても法律は厳格に適用されるため、その危険性を理解しておきましょう。
法律違反による罰則
各専門業法(建設リサイクル法、電気工事業法、浄化槽法など)には、無登録・無届出で営業した場合の罰則が定められています。
これらに違反した場合、「過料(行政罰としての金銭罰)」が科されることが一般的です。しかし、悪質なケースや是正勧告に従わない場合などには、「懲役刑」や「罰金(刑事罰)」の対象となる可能性もゼロではありません。法律で定められた手続きを無視する行為は、決して軽微な違反では済まされません。
取引上の信用失墜
罰則以上に深刻なのが、取引先からの「信用失墜」です。
コンプライアンス(法令遵守)が重視される現代において、必要な届出や登録を行っていない事業者は、元請け企業や発注者から「法律を守れない事業者」と見なされます。
・ 取引停止:元請け企業は、下請けが法令違反を犯していると自社の監督責任も問われるため、無登録・無届出の事業者との取引を即座に停止する可能性が高いです。
・ 新規受注の困難:一度「ルール違反」のレッテルが貼られると、新たな取引先を開拓することも困難になります。
たった一つの手続き漏れが、これまで築いてきた信頼関係と事業基盤を一瞬で失う原因になり得ます。
届出で十分?「建設業許可」取得を検討すべきタイミング
現在は「軽微な建設工事」の範囲内で、必要な「届出」や「登録」のみで事業を行っている個人事業主の方も、事業の将来を考える上で「建設業許可」の取得を検討すべきタイミングが訪れます。

500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合
最も明確なタイミングは、事業が軌道に乗り、請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)を超える工事を受注する見込みが出てきた時です。
500万円以上の工事は「軽微な建設工事」に該当しないため、受注する前に建設業許可を取得しなければなりません。無許可で契約・施工すると建設業法違反となり、重い罰則の対象となります。「チャンスが来たら取得しよう」ではなく、事業拡大の計画段階から準備を進める必要があります。
元請けとして他の下請け業者を使いたい場合
自身が元請けとなり、他の専門工事業者(下請け)を使って工事全体を管理する場合も、許可取得を検討すべきタイミングです。
特に、元請けとして受注した工事のうち、一定額以上(下請代金の総額が4,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請けに出す場合は、建設業許可に加えて「特定建設業許可」が必要になります。そこまで大規模でなくとも、元請けとして工事全体を管理する立場になることは、対外的な信用力の証明として建設業許可が求められる第一歩です。
[出典:[建設業法施行令 第三条 | e-Gov法令検索]
公共工事の入札に参加したい場合
事業をさらに安定・拡大させるために、国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加したいと考える場合、建設業許可は必須条件です。
公共工事の入札参加資格を得るためには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要があり、この経審を受ける前提として建設業許可を取得していなければなりません。届出や登録だけでは公共工事の入札市場には参入できないため、許可取得は必須のステップとなります。
まとめ:個人事業主は「許可」と「届出」の判断が重要
個人事業主として建設業を営む上で、自身が行う工事の内容を正確に把握することが極めて重要です。
- 個人事業主が押さえるべき最終チェックポイント
・ 個人事業主であっても、請負金額が500万円未満の「軽微な建設工事」であれば、原則として建設業許可は不要です。
・ ただし、軽微な工事であっても、「解体」「電気」「浄化槽」などの特定の専門工事を行う場合は、建設業許可とは別に、各業法に基づく「届出」や「登録」が必須となります。
・ 必要な届出や登録を怠ると、法律による罰則だけでなく、元請けや顧客からの信用を失うという重大なリスクを負います。必ず自身の業務内容を確認してください。
・ 将来的に500万円以上の工事を受注したい、元請けになりたい、公共工事に参加したいと考えるなら、届出や登録の先にある「建設業許可」の取得を計画的に検討する必要があります。
まずはご自身の事業が、建設業許可が必要か、あるいは「届出」や「登録」で対応すべきかを正しく判断することから始めましょう。
建設業の届出に関するよくある質問
Q. 個人事業主から法人成りした場合、届出や登録は引き継げますか?
A. 引き継げません。個人事業主としての届出・登録は廃業の手続きを行い、新しく設立した法人として、再度、新規の届出・登録を行う必要があります。法人と個人は法律上別人格として扱われるため、手続きも個別に行わなければなりません。
Q. 届出を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. メリットは、複雑な書類作成や要件確認、窓口への提出代行を専門家に任せられる点です。これにより、申請の不備による時間的損失を防ぎ、ご自身は本業である建設業務に集中できます。特に要件(技術管理者の資格など)が複雑な場合や、日中忙しくて役所に行く時間がない場合には有効な選択肢です。
Q. 届出を忘れていました。今からでも間に合いますか?
A. 無届出・無登録の状態で営業を続けることはできません。法令違反の状態です。届出を忘れていたことが判明した時点(あるいは指摘された時点)で、すぐに業務を停止し、管轄の行政窓口(都道府県の担当課など)に事実を報告し、速やかに手続きを行うよう相談してください。悪質と判断されると罰則の対象となりますが、誠実に対応することが重要です。





