積算とは?建設業での役割と基本プロセス
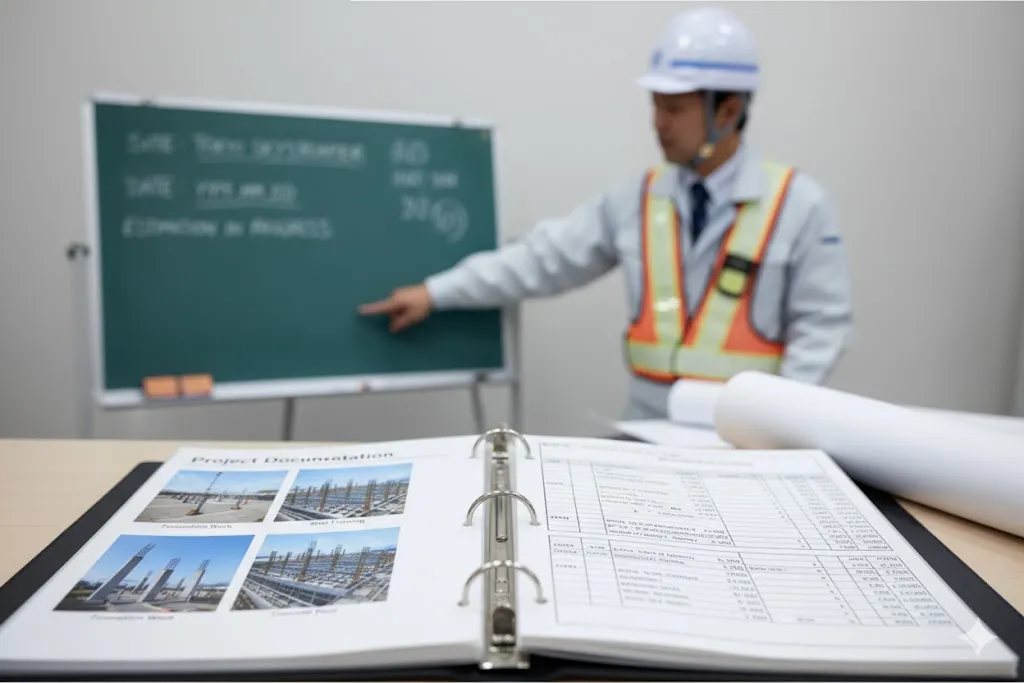
この記事の要約
- 積算は建設工事にかかる原価を算出する事業の土台となる業務
- 利益を上乗せして発注者に提示する「見積」とは目的が異なる
- 図面の読解から数量拾い出し、単価調査を経て工事費を算出
- 目次
- 建設業における積算とは?工事費用の根幹をなす重要な業務
- 積算の目的と建設業での重要性
- 工事価格が決定される仕組み
- 【比較表】「積算」と「見積」の明確な違いとは?
- 積算:工事費用の「原価」を算出する作業
- 見積:利益などを加えた「提出金額」を算出する作業
- 積算と見積の関係性(表で整理)
- 建設業の積算で算出する工事費用の内訳
- 直接工事費(材料費・労務費・直接経費)
- 間接工事費(共通仮設費・現場管理費)
- 一般管理費
- 積算業務の基本的な5ステップ【HowTo】
- ステップ1:設計図書(図面・仕様書)の読解
- ステップ2:数量の拾い出し(拾い業務)
- ステップ3:単価の調査と決定
- ステップ4:工事費内訳書の作成
- ステップ5:集計と最終確認
- 積算担当者に求められるスキルと読者のよくある不安
- 建築・土木に関する専門知識
- 正確な計算能力と高い注意力
- 情報収集力とPCスキル
- まとめ
- 積算に関するよくある質問
- Q1. 積算の学習におすすめの方法はありますか?
- Q2. 積算業務は未経験でも可能ですか?
- Q3. 積算と見積はどちらが重要ですか?
- Q4. おすすめの積算ソフトはありますか?
建設業における積算とは?工事費用の根幹をなす重要な業務
建設プロジェクトの費用を正確に把握し、事業の成功を左右する極めて重要な業務が「積算」です。しかし、その具体的な内容や「見積」との違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは、積算が建設業においてどのような役割を担っているのか、その定義と目的から詳しく見ていきましょう。
積算の目的と建設業での重要性
積算の最大の目的は、設計図や仕様書をもとに、その工事にかかる「原価(=実際にかかる費用)」を算出することです。
これにより、適正な予算設定、実行可能な工事計画の立案、そして最終的な利益の確保が可能になります。会社がどれくらいの費用で工事を完成させられるかを把握するための、いわば「事業の生命線」です。正確な積算なくして、健全な建設事業は成り立ちません。
工事価格が決定される仕組み
建設工事の最終的な価格(契約金額)は、積算によって算出された「工事原価」に、企業の経費や利益となる「一般管理費」などを加えて決定されます。
つまり、積算は顧客に提示する工事価格全体の土台となる、最初のステップなのです。この土台が不正確だと、最終的な利益が圧迫されたり、逆に高すぎて受注機会を失ったりするリスクが生じます。
【比較表】「積算」と「見積」の明確な違いとは?
建設業界で「積算」としばしば混同される言葉に「見積」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と算出する内容が明確に異なります。この違いを理解することが、建設業の価格決定プロセスを把握する鍵となります。両者の定義と関係性を正しく理解し、使い分けられるようになりましょう。
積算:工事費用の「原価」を算出する作業
積算は、あくまでも社内向けの資料として、工事に必要な費用そのものを算出する作業です。具体的には、設計図や仕様書から必要な材料の数量を割り出し、その単価を掛けて「材料費」を、必要な職人の人数と時間から「労務費」を算出します。このように、必要なコストを一つひとつ客観的なデータに基づいて積み上げていくのが積算です。
見積:利益などを加えた「提出金額」を算出する作業
一方、見積は、積算で算出した工事原価に、企業の経費や利益(一般管理費など)を上乗せし、発注者に提示する金額を算出する作業です。これは社外向けの「契約金額」の提案書となります。積算が「いくらかかるか」の計算であるのに対し、見積は「いくらで請け負うか」という会社の意思決定が含まれる点が大きな違いです。
積算と見積の関係性(表で整理)
以下の表は、「積算」と「見積」の違いをまとめたものです。積算が見積作成の基礎となる関係性であることがわかります。
| 項目 | 積算 (Cost Estimation) | 見積 (Quotation) |
|---|---|---|
| 目的 | 工事原価を正確に算出する | 発注者に契約金額を提示する |
| 算出対象 | 工事にかかる費用そのもの(原価) | 原価+一般管理費・利益 |
| 提出先 | 主に社内(実行予算の策定など) | 発注者(施主) |
| 位置付け | 見積を作成するための基礎となる作業 | 積算結果を基に作成される提案 |
建設業の積算で算出する工事費用の内訳
積算業務では、工事費用を大きく3つのカテゴリーに分けて算出します。これらの費用構造は、国土交通省が定める「公共建築工事積算基準」などでも定義されており、業界の標準的な考え方となっています。それぞれの費用が何を指すのかを理解することで、積算の精度と透明性が高まります。
直接工事費(材料費・労務費・直接経費)
工事の対象となる建設物そのものを造るために、直接的に関わる費用です。直接工事費は、主に以下の3つで構成されます。
- 直接工事費の構成要素
・材料費:鉄骨、コンクリート、木材、内装材など、工事に使用する資材や製品そのものの費用。
・労務費:工事現場で実際に作業を行う職人や作業員に支払われる賃金や手当。
・直接経費:機械のリース代やレンタル費、特許使用料、水道光熱費など、材料費・労務費以外で工事に直接かかる費用。
間接工事費(共通仮設費・現場管理費)
工事全体を支えるために間接的に必要となる費用で、工事完了後には形として残らないものが中心です。間接工事費は、以下の2つに大別されます。
- 間接工事費の構成要素
・共通仮設費:仮設事務所や倉庫、足場、養生、工事用フェンス、安全対策など、工事に共通して必要となる仮設物にかかる費用。
・現場管理費:現場監督や現場事務員の人件費、事務所の通信費、事務用品費、交通費など、現場を管理・運営するために必要な費用。
一般管理費
工事原価(直接工事費+間接工事費)には含まれない、企業全体を維持・運営するための費用です。具体的には、本社スタッフの人件費や役員報酬、事務所の家賃、広告宣伝費、福利厚生費などがこれにあたります。積算で算出した工事原価に、この一般管理費と企業の利益を加えて、最終的な見積金額が決定されます。
[出典:国土交通省「公共建築工事積算基準等」]
積算業務の基本的な5ステップ【HowTo】
正確な積算は、定められた手順に沿って論理的に作業を進めることで実現します。ここでは、積算業務の基本的な流れを5つのステップに分けて、各工程の目的と具体的な作業内容を解説します。このプロセスは、小規模な工事から大規模なプロジェクトまで共通する、積算業務の土台となります。

ステップ1:設計図書(図面・仕様書)の読解
・目的:
工事の全体像、品質要求、仕様を正確に把握すること。
・作業内容:
設計図(平面図、立面図、断面図など)と仕様書(特記仕様書、標準仕様書)を照合し、使用する材料、寸法、工法、仕上げのレベルなどを詳細に確認します。この段階での見落としや誤読は、後工程すべての精度に致命的な影響を与えるため、最も重要な工程です。
ステップ2:数量の拾い出し(拾い業務)
・目的:
図面や仕様書に基づき、工事に必要な資材や手間をすべて数値化すること。
・作業内容:
工事に必要な資材の数量(コンクリートの体積[m³]、壁紙の面積[m²]、配管の長さ[m]、建具の個数[箇所]など)を、項目ごとにすべて拾い出します。この作業は「拾い(ひろい)」と呼ばれ、非常に地道ですが、積算の根幹をなす重要な工程です。
ステップ3:単価の調査と決定
・目的:
拾い出した数量に乗じる、客観的で適切な単価を設定すること。
・作業内容:
拾い出した各項目の数量に、それぞれの単価を掛け合わせます。単価は、「建設物価」といった専門誌や、過去の取引データ、仕入先からの見積などを参考に、市場価格や地域差、物価変動を考慮して決定します。労務費については、国土交通省が公表する公共工事設計労務単価などが基準となります。
ステップ4:工事費内訳書の作成
・目的:
各工事項目にかかる費用を明細化し、工事全体の費用構造を可視化すること。
・作業内容:
工事項目(例:「基礎工事」「鉄骨工事」など)ごとに、「数量 × 単価 = 金額」を算出し、工事費内訳明細書としてまとめます。これにより、どの工事にどれくらいの費用がかかるのかが一目瞭然となり、費用の妥当性を検証する際の重要な資料となります。
ステップ5:集計と最終確認
・目的:
算出したすべての費用を集計し、計算ミスや拾い漏れがないか最終チェックを行うこと。
・作業内容:
すべての項目の金額を合計し、直接工事費や間接工事費を算出し、工事原価全体を確定させます。最後に、計算ミスや拾い漏れ、単位の間違いなどがないか、可能であれば別の担当者がダブルチェックを行うなど、入念に最終確認をします。
積算担当者に求められるスキルと読者のよくある不安
「積算業務は専門的で難しそう」という不安を持つ方もいるかもしれません。確かに高い専門性は必要ですが、適切なスキルを体系的に身につけることで、誰でも建設業界に不可欠なプロフェッショナルを目指すことが可能です。ここでは、積算担当者に特に求められるスキルを解説します。
建築・土木に関する専門知識
図面や仕様書を正しく理解し、そこに書かれていない隠れたコスト(例えば、特定の工法に必要な仮設費用など)まで読み解くためには、建築や土木に関する広範な知識が不可欠です。材料の特性や施工方法、関連法規まで理解していることで、より現実に即した精度の高い積算が可能になります。
正確な計算能力と高い注意力
積算は、膨大な量の数値を扱うため、地道で正確な計算能力が求められます。特に「拾い業務」では、小さな見落としや単位の間違いが、最終的に大きな金額の誤差につながるため、細部にまで気を配る高い注意力と集中力が必要です。
- 積算業務で特に重要な能力
・計算能力:四則演算はもちろん、図形から面積や体積を正確に算出する能力。
・注意力:図面の細かい注記や仕様書の特記事項を見落とさない慎重さ。
・忍耐力:膨大な量の数値を長時間にわたって扱い続けることができる力。
情報収集力とPCスキル
建設資材の価格や職人の労務単価、新しい工法は常に変化しています。そのため、常に最新の情報を収集し続ける姿勢が重要です。また、現代の積算は専用の積算ソフトや表計算ソフト(Excelなど)で行うのが一般的なため、これらのツールを効率的に使いこなす基本的なPCスキルも必須となります。
まとめ
この記事では、建設業における積算の役割と基本的なプロセスについて、見積との違いや必要なスキルを交えながら解説しました。
・積算とは、工事にかかる「原価」を算出し、適正な予算や利益を確保するための、事業の土台となる重要な業務です。
・見積との違いは、積算が「社内向けの原価計算」であるのに対し、見積は「社外向けの利益を含んだ提案金額」である点にあります。
・積算プロセスは、図面の読み込みから始まり、数量の拾い出し、単価調査、内訳書作成、そして最終確認という論理的なステップで進められます。
正確な積算は、適正な利益を確保し、建設プロジェクトを成功に導くための第一歩です。この機会に、その重要性を再認識し、日々の業務の改善やスキルアップに繋げていきましょう。
積算に関するよくある質問
Q1. 積算の学習におすすめの方法はありますか?
A1. まずは市販の書籍で積算の基礎知識を学ぶことから始めるのがおすすめです。その後、「建築積算士」などの関連資格の取得を目指すことで、体系的な知識とスキルを身につけることができます。資格学習は網羅的な知識の習得に繋がりますが、最も効果的な学習方法は、実務経験を通して生きた知識を積むことです。
Q2. 積算業務は未経験でも可能ですか?
A2. 未経験から挑戦することは可能です。ただし、建築や土木に関する基礎知識は業務を覚える上で必須となるため、事前に学習しておくことが望ましいです。多くの企業では、アシスタントとして先輩社員の補助業務から始め、実務を通して少しずつ専門知識を身につけていくのが一般的なキャリアパスです。
Q3. 積算と見積はどちらが重要ですか?
A3. どちらも建設事業において不可欠であり、優劣をつけることはできません。ただし、役割が明確に異なります。正確な「積算」がなければ、適切な「見積」を作成することはできず、利益の出る受注は不可能です。その意味で、すべての土台となる「積算」は、事業の根幹を支える非常に重要な業務と言えます。
Q4. おすすめの積算ソフトはありますか?
A4. 積算ソフトは、対象とする工事の種類(建築、土木、電気、設備など)によって多岐にわたります。代表的なものには、建築用では「HEΛIOΣ(ヘリオス)」や「本丸EX」、土木用では「Gaia(ガイア)」シリーズなどがあります。多くのソフトで無料体験版が提供されているため、自社の業務内容に合うか、操作性は良いかなどを比較検討することをおすすめします。





